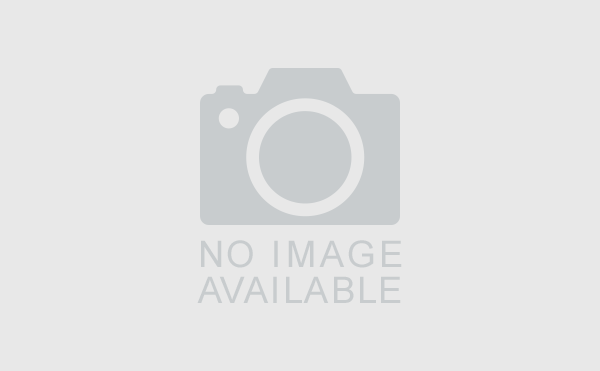負担がついている遺言の相続税の課税関係実務 負担付き遺贈の取扱い
懇意な先輩税理士先生からご質問をいただきました。
質問の趣旨は「負担付きの遺贈がある場合の相続人の負担額が、相続税の課税上債務控除できるかどうか」です。

◇相続税専門 岡田隆行税理士事務所◇ 仕事のお申し込み
【事例】 次の内容の遺言がある場合の相続税の課税関係
相続財産のうち○○市○○町○○番地所在の家屋(貸家 、月額賃料20万円)及びその底地を長男に相続させる。長男はその代償として次男に賃料のうち月額10万円を次男に渡す。
Table of Contents
債務の額を定期金の評価方法で評価?
先輩税理士先生の考えでは、この二男に渡す月額10万円、年額120万円を二男の平均余命年数を用い、定期金の評価方法(相続税法§24)に準じた方法により債務の額を計算して控除するというものでした。
しかし、このとおり債務控除が可能なのであれば、このスキームを用いると、不当に相続税額を減少させることが可能となってしまいます。
確実な債務でないとNG
次の理由からこの負担付き遺贈の負担分の債務控除はできないものと考えられます。
(1)遺言により長男に課せられた負担は、遺言に基づく負担付遺贈または代償分割の一種と考えられる。
(2)しかし、この支払義務は、相続開始時点で被相続人が負っていた債務ではなく、かつ法律上当然に発生する債務でもない。
(3)税務上は、長男が遺贈または取得した財産に付された負担として整理されるため、相続税の債務控除の対象にはならないと考えられる。
定額を渡すのであれば代償財産として課税
このケースで、長男が負担する額がたとえば1,000万円という定額で明示されていた場合はどうでしょうか。
上述の(1)のとおり、負担付きの遺贈は遺言に基づく代償分割の一種であると考えられます。
したがって、長男は賃貸物件を相続する代償として、1,000万円を次男に交付すると考えれば、長男のマイナスの代償財産1,000万円、二男のプラスの代償財産1,000円を相続税の申告書(第11表)に計上すればよいことになります。
【参考】
相続税の課税上控除できる債務の取扱いとしてはつぎのとおりです。
(国税庁HP タックスアンサーNo.4126「相続財産から控除できる債務」より抜粋)
◇控除できる債務
被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるもの。
◇債務控除できる人
財産を取得した時に日本国内に住所がある、債務などを負担することになる相続人や包括受遺者です。
相基通11の2-7(負担付遺贈があった場合の課税価格の計算)
負担付遺贈により取得した財産の価額は、負担がないものとした場合における当該財産の価額から当該負担額(当該遺贈のあった時において確実と認められる金額に限る。)を控除した価額によるものとする。
※記事の内容は更新日現在の法令にもとづいて作成していますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当事務所では一切の責任を負うことはできませんのでご了承ください。
◇相続税専門 岡田隆行税理士事務所◇ 仕事のお申し込み

【相続税専門】税理士 岡田隆行
国税局・税務署での32年間の資産税(相続税・贈与税)事務の経験を活かし、相続税に関する困りごとの解消に尽力します。
事務所は高松市国分寺町、趣味は料理とバイクです。